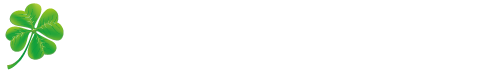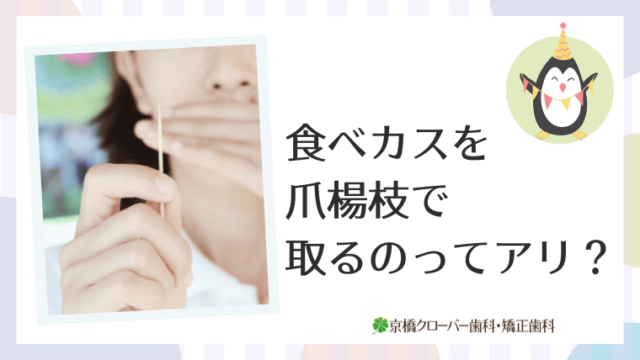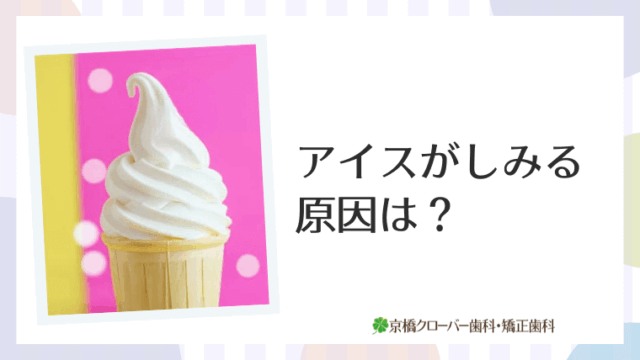親知らずの抜歯はするべき?
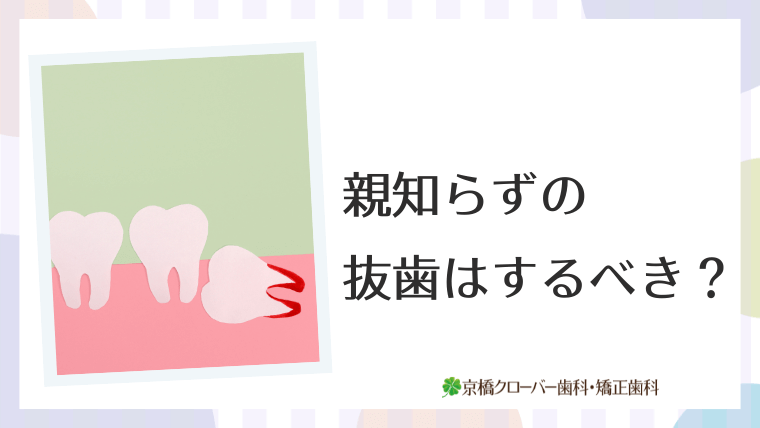
親知らずの抜歯について悩む大人の方は多いでしょう。生えてきて痛みや腫れなどの症状が出た方、反対に症状はないけど抜いた方がいいのかと迷う方、様々です。親知らずの抜歯は簡単なケースから難しいケースまであり、抜くか抜かないかの診断基準などご紹介します。
親知らずの抜歯とは何か
親知らずとは、第三大臼歯(智歯:ちし)で、前歯から数えて最後方、すなわち奥歯の更に奥に生える歯を指します。一般的には17〜24歳頃に萌出します。親知らずが口腔内で正常に機能し、清掃可能で他の歯に悪影響を与えない場合は抜歯しないこともあります。ただし、現代人は顎が小さいためトラブルを引き起こしやすく、その際親知らずの抜歯が検討されます。
- 炎症や痛みが出る
- 隣接する歯が虫歯や歯根吸収になる
- 智歯周囲炎や嚢胞(のうほう)などの発生
- 顎関節症や歯並びの乱れ
親知らずの抜歯は、単純に歯が露出していて抜く比較的容易なケースから、顎の奥深くまたは横向きに生えているため、骨を削って取り出すような難しいケースまで、多様な術式と手法があります。抜歯は侵襲を伴う処置であり、身体的な面で合併症のリスクもあります。そのため、抜歯を行うかどうかは、歯科医師との十分な相談のもとで判断すべきです。
親知らずを抜くべき?残すべき?判断基準
親知らずを抜くか、残すかを判断する基準はいくつかあります。すべての親知らずを無条件に抜くわけではありません。状況やリスクを見極めて判断することが重要です。
抜歯した方がよい例
抜歯をしたほうがトラブルを防ぎやすいと判断される典型的なケースをご紹介します。
- 親知らずの周囲の歯肉に腫れが見られ、痛む
- 親知らずが虫歯になっている
- 親知らずが隣の歯を押して痛みや圧迫感を生じている
- 親知らずが歯肉や頬の内側を傷つけている
- レントゲンで親知らずの周囲に黒い影がある
- 隣接する第二大臼歯が虫歯になっており、その原因が親知らずとの位置関係による
- 将来的に矯正治療や義歯治療を考えることから、親知らずが支障になる可能性が高い
抜歯しなくてもよい例
次のような場合は、親知らずを将来的に残しておく選択肢も考えられます。
- 真っすぐに生えて上の歯と噛み合っており、機能的に問題がない
- 骨に完全に覆われていて将来的に萌出の見込みが薄く問題がない
- 矯正治療で利用できる可能性がある
- 歯牙移植のドナーとなる可能性がある
- 抜歯によるリスクと比較した結果、リスクのほうが高いと予測される
抜歯にはリスクが伴うため、残す判断をすることも十分にあり得ますが、残す場合も定期的な観察とレントゲンによる診断が必須です。
抜歯が必要になる主な症状や理由
親知らずを抜く必要性が出てくる代表的な症状や理由を、具体例を交えて説明します。
抜歯を考えるきっかけになる主な症状
このような症状や理由が一つでも認められる場合、抜歯の適応を検討すべきです。
炎症や腫れ
親知らずが半分のみ出ている、または完全に出ない状態では、歯と歯肉の間に隙間ができ、そこから細菌が入り込み、炎症を起こすことがあります。これを智歯周囲炎と呼び、歯肉が赤く腫れたり、痛み、発熱、口が開きにくいといった症状が出ることがあります。
虫歯
親知らずは口の奥に位置するため、歯ブラシが届きにくく、汚れが残りやすく、虫歯になりやすいです。親知らずと接している隣の第二大臼歯にも虫歯を広げることがあります。
圧迫、痛み、違和感
親知らずが斜めや横向きに生えていると、隣の歯を押して違和感や痛みを引き起こすことがあります。また、咬み合わせや歯列全体に影響を与えることもあります。
口臭、不衛生
ブラッシングが難しい位置であるため汚れが蓄積し、口臭の原因となることがあります。
嚢胞や嚢胞性変化
歯の根である根尖あるいは歯根周囲に嚢胞が形成され、骨を溶かしたり、隣接する歯を圧迫することがあります。
隣接歯の根を吸収
親知らずと隣の歯の根が接近している場合、親知らずの圧力によって隣の歯の根がやせてしまうことがあります。
親知らずの抜歯の流れ及び方法
親知らずの抜歯は、ケースによって方法が大きく異なります。一般的な流れと代表的な術式を紹介します。
抜歯のための事前準備
抜歯のために行う準備をご紹介します。
診査及び診断
口腔内を検査し、歯の状態を確認し、X線および必要に応じてCT撮影を行います。例えば、親知らずの歯根が上顎洞や神経に接近しているかどうかもしっかりチェックします。
全身状態の確認や問診
全身疾患の持病があるのか、服薬しているのか、アレルギーはないか、出血傾向や妊娠の有無などを歯科医師が把握します。
説明と同意
抜歯のリスクや合併症、術後の注意点を詳しく説明し、患者の同意を得ます。
麻酔準備
局所麻酔は必須ですが、恐怖心や嘔吐反射の強い方には静脈内鎮静法を用いることがあります。意識を完全になくすのではなく、うとうとした感覚で処置を行う方法です。
抜歯方法や術式
抜歯方法は難易度によって変わりますが、代表的なものをまとめます。
| 術式 | 特徴や適応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 抜歯鉗子等でそのまま抜く単純抜歯 | 歯が完全に萌出し、まわりの骨や歯肉に障害がないケース | 最もリスクが小さい |
| 剥離・分割抜歯 | 歯冠を剥がしたり、歯を分割して除去する手法 | 歯根が複雑な形状や骨に埋まっているときに用いる |
| 骨を削る外科抜歯 | 骨を部分的に削り、切開して抜歯 | 骨内に埋まっている埋伏歯など難症例に適用 |
| 段階的抜歯の二回法 | 一度にすべてを抜かず、段階的に処置する | 術後リスクを抑えたい場合や感染リスクの高い部位で採用されることがある |
抜歯の処置の流れ
- 麻酔を行う
- 歯肉を切開し、骨を露出させて剥離
- 親知らずを分割したり、そのまま除去
- 骨の整形や損傷部の修正
- 止血を行う
- 縫合
- 抜歯箇所にガーゼを当て圧迫止血を行う
処置時間は症例の複雑さにより大きく変わり、単純なケースであれば10~20分程度、複雑な埋伏智歯などでは30分以上かかることもあります。
抜歯によるリスクや合併症
親知らずの抜歯には、さまざまな合併症やリスクがゼロではありません。
主な合併症
合併症についてご紹介します。
疼痛
術後2~3日において痛みがピークになり、それ以降徐々に軽減します。痛みの程度は症例によって異なり、鎮痛薬でコントロール可能な範囲から、1週間以上続くものまであります。
腫れ
軟組織の腫れは術後1〜2日が最大で、1〜2週間かけて軽減していきます。冷却は有効ですが、冷やしすぎて血行不良にしないよう注意が必要です。
発熱
抜歯後の軽い発熱は、菌血症(細菌が一時的に血中に入ること)によることが多く、通常は自然に改善します。特定の組織や臓器の中で細菌が増殖するケースもまれにあります。高熱が長期間続く場合は注意が必要です。
後出血
麻酔薬の血管収縮作用が切れたタイミングで出血が起こることがあります。ガーゼ圧迫止血を行い、それでも止まらない場合は歯科医院へ連絡し、早めの受診が必要です。
神経麻痺
下顎の親知らずでは、下歯槽神経(下唇やオトガイ部の感覚を司る神経)を傷つける可能性があります。報告上、確率は0.5~0.6%程度と言われることがあります。また、舌神経が損傷されると舌の知覚や味覚に影響が出ることがあります。リスクはまれですが、完全回復しないケースも報告されています。
上顎洞穿孔
上顎洞という副鼻腔の一部に上顎の親知らずの根が接している場合、抜歯窩と上顎洞がつながってしまうことがあります。空気、水、飲食物などが鼻に交通してしまい、放っておくと蓄膿症を引き起こすことがあります。小さな穿孔なら自然閉鎖することが多いですが、大きな穿孔で閉鎖しなければ穴をふさぐ手術が必要になります。
開口障害や嚥下痛
炎症や腫れが周囲に波及し、口を開きにくくなったり、食べ物の飲み込みの際に痛みが出ることがあります。
皮下出血斑
抜歯により皮下出血を起こし、頬やあご、首にあざが広がることがあります。通常1~2週間ほどで改善します。
手前の歯の痛みや知覚過敏
抜歯後しばらく、隣接する歯が痛んだり、知覚過敏になることがあります。これは、抜歯により隣の歯根に刺激が及ぶためです。
残根
抜歯の際に歯根の一部が残ってしまうことがあります。場合によっては後日取り除く必要が生じます。
感染
抜歯後の感染リスクは、特に下顎の親知らずや骨内に埋まっていた場合で高まる傾向があります。糖尿病や免疫抑制状態の方、長時間手術になった場合などは注意が必要です。
顎関節脱臼
大きく口を開けすぎてしまうと、まれに顎関節の脱臼を起こすことがあります。
皮下気腫
抜歯器具から空気が入り、皮下組織に気体が貯留することがあります。顔や頸部が腫れ、違和感や痛みを伴うことがあります。
拡大すれば呼吸困難など重篤な状態になる可能性もあるため、注意を要します。
これらのリスクを最小限にするためには、適切な事前診断、経験ある術者の選定、慎重な処置および術後管理が不可欠です。
術後ケアと注意点
抜歯後に適切なケアを行うことによって、回復を早め、合併症を予防することができます。
術後すぐ(初日〜数日)
ガーゼ圧迫止血
抜歯直後~麻酔が切れ始める頃に出血が起こる場合があります。ガーゼを丸めて患部に当て、30分程度圧迫して噛むようにします。適切に圧迫できていないと止血が不十分になります。
冷却
腫れを抑えるため、術後1〜2日程度は患部近傍を冷やします。ただし、冷やしすぎると血行が悪くなり治癒が遅延するため、水で冷やす程度にします。
安静
強い運動やうがい、入浴、高温環境、飲酒などは血流を促進し、腫れや出血を助長するため控えます。
鎮痛薬や抗炎症薬
痛みが出る前から予め服用しておくことで疼痛の持続を抑制します。症状に応じて、痛くなり始めたときに追加で服用する形が一般的です。
抗菌薬
術後感染リスクが高いと判断される場合には、抗菌薬を処方されることがあります。
術後中期~回復期
口腔ケア
処置部分は強くこすらないよう注意し、軽くうがいをする程度にします。処方された抗菌性のうがい薬を用いることもあります。
食事
柔らかく刺激の少ない食事を心がけます。おかゆやスープ、ヨーグルトなどを取るようにし、硬いものや刺激物は当面の間避けましょう。
鼻をかむ、くしゃみ、咳
特に上顎洞へのリスクがある場合は、強く鼻をかむことや、大きなくしゃみはよくありません。くしゃみや咳が我慢できない場合は口を開けて軽く行うなど配慮しましょう。
定期診察
数日後に術後のチェックを受け、縫合糸の除去や感染所見の確認を行います。
このような状態であればすぐ受診を!
このような異常が見られた場合は、速やかに抜歯をした歯科医院や専門施設を受診しましょう。
- 出血が止まらない
- 発熱が38℃を超えて数日続いている
- 強い痛みや腫れが増している
- 麻痺やしびれが改善しない
- 呼吸困難や嚥下困難
抜歯を回避できる可能性と管理法
親知らずを無理に抜かずに、問題を未然に防ぎながら持たせる選択肢もあります。
定期観察と検査
- 年1〜2回程度、口腔内検査とレントゲン撮影を行い、親知らずおよび隣接歯の状態を確認
- 症状が出ていなくても、将来リスクを予測するために定期チェックは不可欠
衛生管理の徹底
- 親知らず周囲は特に歯ブラシやフロス、歯間ブラシなどを使用し重点的に清掃
- 歯科医師に相談し、抗菌性うがい薬を活用
- 食後はもちろん、就寝前には特に丁寧に歯を磨く
炎症予防
- 智歯周囲炎を起こさせないよう、違和感や軽い痛みがあれば早めに受診
- 炎症が出た際は速やかに治療を受け、炎症を繰り返させない
矯正や咬合調整との連携
- 矯正治療を行う場合、位置の関係によっては親知らずが歯列に影響を及ぼすため、矯正歯科医師との情報共有が望ましい
- 噛み合わせのバランスを見ながら、将来的に親知らずを支えに使えるかどうかを検討
これらを適切に行えば、すぐに親知らずを抜かなくとも問題なく維持できるケースもあります。
まとめ

親知らずは必ず抜歯しなければならないわけではないが、将来的なリスクを抑えるために抜歯が適応となるケースがあります。だし、抜歯には一定のリスクや合併症が伴うため、適切な診断と慎重な術式選択が重要です。担当する歯科医師に親知らずの状態を説明してもらい、抜歯しなかった場合に起こりうるリスクとそれを抑える方法を確認し、そのうえでどちらがより適しているかを考えましょう。