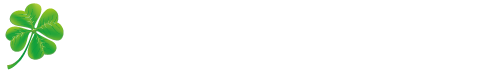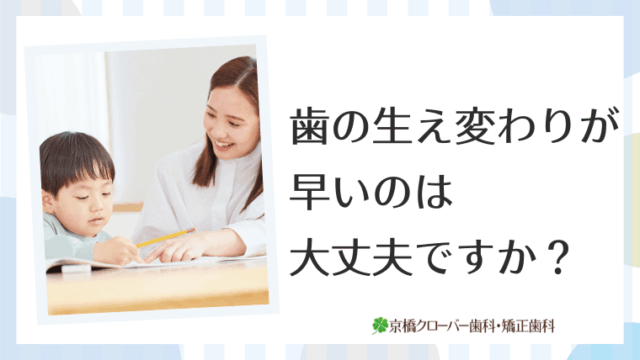乳歯が抜けた後、その歯をどうすべきか、戸惑うパパやママもおられるでしょう。子どもの歯は心身の成長とともに乳歯から永久歯へと生え変わるのが自然なサイクルです。成長の証と言えますが、そのときの対応や、保管方法、反対にすぐに歯科受診をしなければならないケースについて説明します。
乳歯が抜けるのは成長のサイン
乳児期に生えた乳歯が1本抜けた時、それはもうすぐ大人の歯である永久歯が生えてくるというひとつの成長の目印です。一般的には6歳ごろから乳歯が抜け始め、12歳あたりまでに多くの歯が生え変わっていきます。 親としては抜けた後のケアや次の歯はどうすればと不安になることも多いですが、正しい理解と適切に対応すれば安心して見守ることができます。子ども自身も少しだけ大きくなったと感じる瞬間となり、親子で前向きに捉えることが大切です。
乳歯の抜ける流れ
乳歯が抜ける流れについてご紹介します。
- 歯の卵となる歯胚は母体の中にいるうちから形成される
- 歯槽骨の中で歯胚はゆっくりと成長して永久歯の歯冠部を形成する
- 歯の根の部分が作られ始めると、乳歯の根を溶かす細胞が現れる
- 永久歯の上にある乳歯の根は細胞により少しずつ溶かされ短くなる
- 乳歯の根が短くなるとグラグラと揺れて抜ける
観察が必要な場合
乳歯の役割を終えて次の永久歯にバトンタッチをするのは自然な流れです。ただし、注意してお子さんの歯を観察しなければならないケースがあります。
- 乳歯がグラグラしているのにずっと抜けない
- 反対側と比べて抜けるのが遅い
- 永久歯が見えてきているのに乳歯が残っている
このような状態であれば、何か歯周組織でトラブルが起きている可能性があります。歯科医院へ相談しましょう。
抜けた直後にまず行うこと
乳歯が抜けた直後は、子どもも親もびっくりしてしまうと思います。歯が抜けた際に出血や痛みを伴うこともあるため、次のような対処を行いましょう。
清潔なガーゼやハンカチで抜けた部分の歯茎を軽く5~10分ほど圧迫して止血を試みる
強いうがいや口をすすぐ動作を避ける
血のかたまりであるかさぶたを流すと再出血の可能性があるため触らない
熱い飲み物やストローを使う飲み物、硬い食べ物など刺激になりやすいものを避ける
手指や舌で抜けた部分を触らないよう、子どもに優しく声かけをする
慌てずゆっくりと落ち着いた様子で見守ることが、余計なトラブルを避ける第一歩です。
抜けた後の口内ケア及び注意点
乳歯が抜けた後は、口の中の環境が少し変化します。抜けたスペースが敏感になったり、周囲の歯や歯茎が影響を受けやすくなります。
歯ブラシで抜けた後を触らない
歯ブラシは抜けた部分そのものを強く擦らず、抜けた部分の周囲の歯を丁寧に磨きましょう。歯が抜けたところの歯茎は敏感になっているため、触らないようにすることが大事です。うがいも冷水ではなく、ぬるま湯で軽く口をすすぐ程度にしてください。強くガラガラと振動させると歯茎には刺激となる場合があります。
[jin_icon_writercolor=”#e9546b” size=”18px”]抜けた穴があることで、隣の歯が少し動きやすくなって歯列の乱れが起きたり、汚れや歯垢(プラーク)が残りやすいということもあります。食後や就寝前の歯磨きを丁寧に行い、フッ素入りの歯磨き粉を活用するなどして虫歯予防も意識しましょう。
抜けた後、体温上昇させない
乳歯が抜けた当日は、体を動かす激しい運動や長時間の入浴を控えておきましょう。それらを行って体温が上昇したり、全身の血流が良くなれば、再出血する可能性や、痛みが強まる場合があるからです。
食事で刺激になるものを食べない
抜けた部分を避けて噛むように子供に伝えましょう。食事は柔らかめのものを準備してください。熱い飲み物以外にも、意外と硬いスナック菓子、炭酸飲料、極端に熱いものや辛いものは抜けた部分の刺激になるため我慢しましょう。
ケアをしておくと、抜けた後のスペースが感染源になったり、隣の歯が動いて永久歯の生えるスペースが狭くなるというリスクを減らすためにも有効です。
永久歯が生えてくるまでの見守りポイント
乳歯が抜けた後、次に登場するのが永久歯です。生え変わりの時期や順番には個人差がありますが、保護者として知っておきたいチェックポイントがあります。
永久歯が出てこない
抜けてから半年以上経っても永久歯が見えてこない、まったく生えてこないという場合は、歯科医院での診察を検討した方が安心です。永久歯が存在しない先天性欠如歯という可能性もあります。 先天性欠如歯を早期に発見できれば、なるべく自分の歯で噛み合わせを作れる矯正治療を行うことができ、影響を最小限にできます。
生え始めの永久歯に要注意
永久歯が生えてきたばかりの頃は、歯質が未成熟で柔らかいため、虫歯になりやすいです。第一大臼歯(6歳臼歯)が生え始めのタイミングは、奥歯の溝に食べかすやプラークが詰まりやすい状態であるため、仕上げ磨きは念入りに行いましょう。
歯並びや噛み合わせにも注意
生えてきたらいいというのではなく、歯並びや噛み合わせにも少しアンテナを張っておきましょう。例えば、乳歯が早く抜けたり、永久歯が変な方向に生えているように感じたり、抜けたスペースがすぐに隣の歯に塞がれてしまうという状態では、後々に矯正や歯並びのケアが必要になる可能性があります。歯並びや噛み合わせが悪ければ、見た目以外にも顎関節に負担がかかり過ぎたり、肩こり、頭痛の原因になることがあります。
生え変わり期には定期的な歯科検診を
歯科医師に生え方、隙間の確保、虫歯や歯質のチェックをしてもらうのがおすすめです。乳歯は抜けたらおしまいではなく、永久歯にバトンタッチする大切な時期を迎えたと捉えて、定期的なプロのケアを受診する方が良いです。
抜けた乳歯の扱い
抜けた乳歯をどうするかは、保護者の悩みどころでもあります。保存するのか、風習に倣うか、処分するのか、それぞれの選択肢について挙げていきます。
保存する場合
抜けた歯を洗って水分を取り、乾燥させた後に専用の乳歯ケースに入れて保管する方法があります。抜けた日付を記入して、成長の記念として残すご家庭も少なくありません。親子で「今日は〇〇の歯が抜けたね」と会話するきっかけになります。
将来の再生医療を視野に入れて歯髄細胞バンクへ預けるという選択肢も紹介されています。乳歯の歯髄には比較的若く元気な幹細胞が含まれているという研究結果があります。
処分、風習として
日本では、上の歯は床下に、下の歯は屋根の上に投げるという風習があります。最近では、集合住宅やマンションでの実施が難しいケースもあるため、風習はせず、処分や保存する家庭も増えています。これは、生え変わる永久歯がまっすぐ上部に生えますようにという願いから来ていると言われます。 では、海外で行われている抜けた歯に関する風習をまとめてみました。
| 地域や国 | 登場キャラクター | 行うこと | 願い及び意味 |
|---|---|---|---|
| アメリカ・イギリスなど英語圏 | トゥースフェアリーという歯の妖精 | 抜けた歯を枕の下に置くと、妖精がやって来てお金やプレゼントと交換してくれる | 成長のご褒美として歯を大切にする心を育てる |
| スペイン・フランス | ねずみの妖精 | 抜けた歯を枕の下に置くと、ねずみが来てコインや贈り物に替えてくれる | 丈夫な歯の象徴であるねずみのように、強く健康な歯が生えるように願う |
| 韓国 | カラスなどの鳥 | 抜けた歯を屋根の上に投げると、カラスが新しい歯を持ってくると言われている | 「強い歯が生えますように」と願う |
| トルコ・中東地域 | おまじないとして埋める | 抜けた歯を学校・モスクなど縁起の良い場所に埋める | 子どもが賢く育ち、立派になるようにという願う |
どちらを選ぶか
保管するか、処分または風習として投げるかは、家庭の文化や考え方によります。
子ども本人が抜けた歯をどうしたいか聞いてあげる
保管する場合は衛生的に洗浄し乾燥させる
保管せずに処分したり、風習を楽しむ場合も、親子で乳歯が抜けた後にする風習の意味を共有しておくと、思い出として残りやすいです。
こんなときは歯科受診を!早めに相談すべきサイン
乳歯が抜けた後も、次のような症状があれば、早めに歯科医院での相談をおすすめします。
- 出血が30分以上止まらない
- 再び出血した
- 抜けた部分の歯茎が腫れている
- 膿が出ている
- 痛みが強い
- 乳歯が抜けて半年以上経っても永久歯がなかなか生えてこない
- 反対側の歯と比べて明らかに遅い
- 抜けた歯の隣の歯が傾き、永久歯が生えるスペースが狭い
- 乳歯が抜ける前に永久歯が先に出てきてしまった
このようなサインは無視してはいけません。早めに歯科医師にチェックしてもらうことで、歯並び、噛み合わせ、永久歯の欠如などの大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ

乳歯が抜けることは、子どもにとっても親にとってもひとつの成長の区切りです。ただし、抜けた後のケアを軽く考えてしまうと、出血や痛み、感染、永久歯の生え方の問題などにつながる可能性があります。抜けた直後にしっかりと対処をし、口内ケアを丁寧に行い、永久歯が生えてくるまで見守ることで、より安心して次のステップへ進めます。
また、抜けた乳歯を記念として保存するか、風習として処分するかをあらかじめ家族で話し合っておくと、子どもにも自分の歯が抜けたんだ、次の歯が来るんだという意識が芽生えやすくなります。この症状があれば歯医者さんに相談をという信号も覚えておけば、どうしよう?と不安になる場面を減らせるでしょう。
お子さんに対して「おめでとう、次の歯生えてくるね」と声を掛けてあげ、健やかな成長を見守ってあげてください。