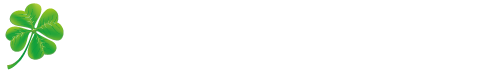歯の生え変わりが早いのは大丈夫ですか?

歯の生え変わりが早い子供がいると、聞いていたよりも早すぎると心配になることはありませんか。歯の生え変わりは成長の証で、おおよそ5~7歳頃から始まると言われています。平均的な歯の生え変わりの時期や、早いと何か悪い影響があるのかなどを含めて詳しくご紹介いたします。
目次
平均的な歯の生え変わり時期はいつ?
歯が生えることを萌出と言いますが、子どもの乳歯から永久歯への生え変わりは発育過程の一環です。しかし、いつ始まるか、どの順番かなど終了する時期にはかなり幅があります。通常、永久歯への生え変わり開始年齢は 5〜7歳ごろからとされることが多いです。最も早い例では 4歳半ごろから、遅い例では、9歳ごろまで乳歯が残る例も珍しくありません。
たとえば前歯や6歳臼歯など、生え変わる順番にも一定の傾向があります。つまり、早い、遅いという判断は、あくまで平均的な時期を目安と比較した相対的なもので、個人差が大きいため、少し時期が早めでも必ずしも異常とは言えません。
歯の生え変わりはどこからが早いの?
歯の生え変わりが早いと言えるラインは、明確な基準があるわけではありませんが、次のような目安が参考になります。
- 4歳未満で乳歯が抜け始める:非常に早く、何らかの異常が関わる可能性も考慮される。
- 5歳で生え変わりが始まる:平均よりやや早めだが、必ずしも問題とならないケースも多い。
ただし、早すぎると感じても、生え変わりの進行速度や 永久歯の発育度合い、あごの成長具合などを含めて総合的に確認する必要があります。乳歯が抜けてもすぐに永久歯が出てこない、あるいは抜けた歯の根が予想と異なる形状だったなどの異常があれば、注意を要します。
早い生え変わりの原因
歯の生え変わりが通常より早い原因はいくつか考えられます。
個人差、成長速度の違い
子どもの成長過程には個人差が大きいです。歯やあごの成長が早い子どもでは生え変わりも早めに始まる傾向があります。
顎や歯の発育の進度が早い
上下の顎骨が早く発達していれば、永久歯が芽を出す準備が整い、生え変わりへの移行がスムーズになるケースがあります。
先天的な要素
歯の萌出や発育に関する遺伝的な影響により、体質的に成長スピードが速い体質を持つ子供もいます。
外傷や事故
事故やケガなどの強い衝撃で乳歯が早期に抜けてしまうこともあり、その結果として生え変わりが早く見える場合もあります。
低ホスファターゼ症(HPP)
骨代謝に関わる疾患である低ホスファターゼ症(HPP:Hypophosphatasia) の可能性が指摘されることがあります。アルカリホスファターゼという酵素がうまく働かず、骨にカルシウムがつきにくくなるため、骨が弱くなる病気です。乳歯がとても早く抜けたり、けいれんを起こすことがある人もいます。血液検査で、この酵素(ALP)の値が低いことが特徴で、重い人から軽い人まで、症状の幅があります。
どのくらいの人がかかる?
出生する子どもの15万人に1人ほどと言われています。日本では100〜200人ほどと考えられてきましたが、今は治療薬ができ長く生きられる患者さんが増えています。
誰に多い?
両親から遺伝子を受け継ぐタイプ(劣性遺伝)が多く、一部は片方の遺伝子だけでも発症するタイプ(優性遺伝)もあります。アルカリホスファターゼという酵素を作る遺伝子に変異があり、その働きが弱くなるのが原因です。
どんな症状?
| 区分 | 主な症状 |
|---|---|
| 骨 | 骨折しやすい/骨の変形/骨の痛み/低身長 |
| 重症の赤ちゃん | 胸が小さく呼吸が苦しくなる/けいれん/体重が増えにくい |
| 歯 | 乳歯が4歳までに抜けてしまう |
| 成人 | 骨折/筋力低下/関節の痛み/関節が腫れて痛む |
治療法は?
以前は対症療法しかありませんでしたが、2015年から酵素補充療法の登場で、重症の患者さんも助かるようになっています。歯が早く抜けてしまう子供には、小児用の義歯が保険適用で使える場合もあります。
HPPにおいては歯のセメント質形成不全のために乳歯の動揺、早期脱落を来すため、小児歯科による管理が必要になります。口腔衛生指導と歯周治療により、動揺歯であっても、永久歯に交換される時期まで乳歯を温存します。乳歯早期脱落に対しては、審美性や、発音機能の獲得、残存乳歯への咬合圧を下げる目的として小児義歯の装着が行われます。
その他の要因
- 栄養状態やホルモンバランスが乱れている
- 歯の萌出順序の乱れや、噛み合わせ、口腔内環境の違い
これらが単独あるいは複合的に関わって、生え変わり開始時期の差異を生じさせます。
早すぎる生え変わりによる影響
歯の生え変わりが早いこと自体が必ずしも悪影響を及ぼすわけではありませんが、注意すべき点やリスクはいくつかあります。
永久歯の萌出異常や位置異常
生え変わりが早すぎると、永久歯が本来の位置で出づらくなったり、横向きや傾斜状態で出てくる場合があります。たとえば、乳歯が抜けたまま長く放置され、隣の歯が傾き、すき間が閉じることで、永久歯の出る方向が乱れるリスクが高いです。
歯並びや噛み合わせへの影響
不適切な萌出位置やスペース不足が続くと、将来的にガタガタ、叢生、乱杭歯などの不正咬合を招く可能性があります。特にあごの成長が追いつかない場合は、矯正治療の必要性が高くなります。
虫歯リスクの上昇
生え変わりの時期には乳歯と永久歯が混在し、歯列がデコボコしやすい状態で、歯の磨き残しが起きやすくなります。生え始めたばかりの永久歯は幼若永久歯(ようじゃくえいきゅうし)と呼ばれる未成熟な歯質で、まだエナメル質や歯根がしっかり完成されていないため、虫歯になりやすい性質を持っています。
保護者の不安と早期対応の難しさ
生え変わり開始が早いと「何か異常ではないか」「将来的な影響は?」という不安を抱く保護者が多くなります。しかし、すべてが治療対象とはなりません。見守ることが適切となるケースも多いため、判断が難しい部分もあります。
どのようなケースで受診すべき?
生え変わりが早いだけで即受診というわけではありませんが、次のようなサインがあれば歯科医院での診察をおすすめします。
乳歯が4歳未満で抜け始めている
抜けた歯の根の形状が極端に細長い、三角形など不自然である
乳歯を抜いた後、2〜3か月たっても永久歯がまったく生えてこない
永久歯が生えてきたが、左右対象でなく傾いて生え、変な方向に向いている
乳歯が抜けないまま、永久歯が隣から出てきてしまった
歯ぐきや歯肉が腫れて痛み、違和感、色が変わっている
子供自身が痛みを訴え、食事や咀嚼に支障が出る
こうしたサインがあれば、レントゲン撮影や口腔内診査を通じて、永久歯の数や位置、あご骨の状態、過剰歯などの有無を確認すべきです。定期的に歯科医院へ通い、早めに異変を察知しやすくすることをおすすめします。
観察すべきポイント
早い生え変わりが見られて気になるサインがあった場合、歯科医院での対処や、ご自宅での観察を行うことが望ましいです。
定期的な歯科健診及びレントゲン検査
萌出状態や永久歯の位置、顎骨の成長度合い、過剰歯や萌出異常の有無を確認できるよう、定期検診を受診しましょう。
抜けた乳歯の根のチェック
抜けたときの乳歯根の状態を観察し、異常な形状や残根片がないかを歯科医師に確認してもらいます。
永久歯の萌出の経過観察
乳歯が抜けたあと、3〜6か月程度を目安に永久歯が出てこないかを見守り、それ以上待っても歯が出てくる気配がなければ対処を検討しましょう。
口腔ケアの強化
生え変わりの時期は歯列がデコボコして磨き残しが増えやすいため、保護者の仕上げ磨きをしっかり行いましょう。歯科医院での高濃度のフッ素塗布や適切な歯磨き指導を受けるのも効果的です。
口腔習癖を改善
唇や舌癖、指しゃぶり、頬杖、口呼吸などは顎や歯列の成長に悪影響を及ぼします。口腔習癖があれば改善を促すように、口腔筋機能療法(MFT)や装置による治療を検討しましょう。萌出異常や永久歯の位置のずれが見られれば、補助的治療である床矯正、部分矯正、誘導矯正などを検討することもあります。
歯の生え変わりと歯並びの関係性
歯の生え変わりが早いことと、将来の歯並びがどのように結びつくかという点を理解しておくべきです。生え変わるタイミングが早かろうと、顎の骨の成長が十分であれば歯並びへの大きな悪影響は抑えられる可能性があります。
反対に、生え変わりが早くても顎の発達がしきっていない場合、萌出スペースが不足し、歯の重なりやずれが発生しやすくなります。将来的な矯正治療を見据え、早期に顎の幅の確保やコントロールを行い、スペースを確保する床矯正を併用する選択肢もあります。ただし、早い段階で矯正をすること自体が最適とは限らず、患者さんの成長の見極めやメリット、デメリットなどを考えたうえでの判断が重要です。
まとめ

歯の生え変わりが早いと感じたとき、過度に不安になる必要はありません。個人差や成長速度の違いが背景にあることが多いです。しかし、4歳未満の生え変わりであったり、抜けた歯根の異常、萌出遅延、傾斜萌出といった異変が見られる場合は、早めに小児歯科での診断を受けましょう。定期健診と適切な口腔ケア、そして必要に応じた補助的な治療を併用することで、将来の歯並びへの悪影響を低減できます。